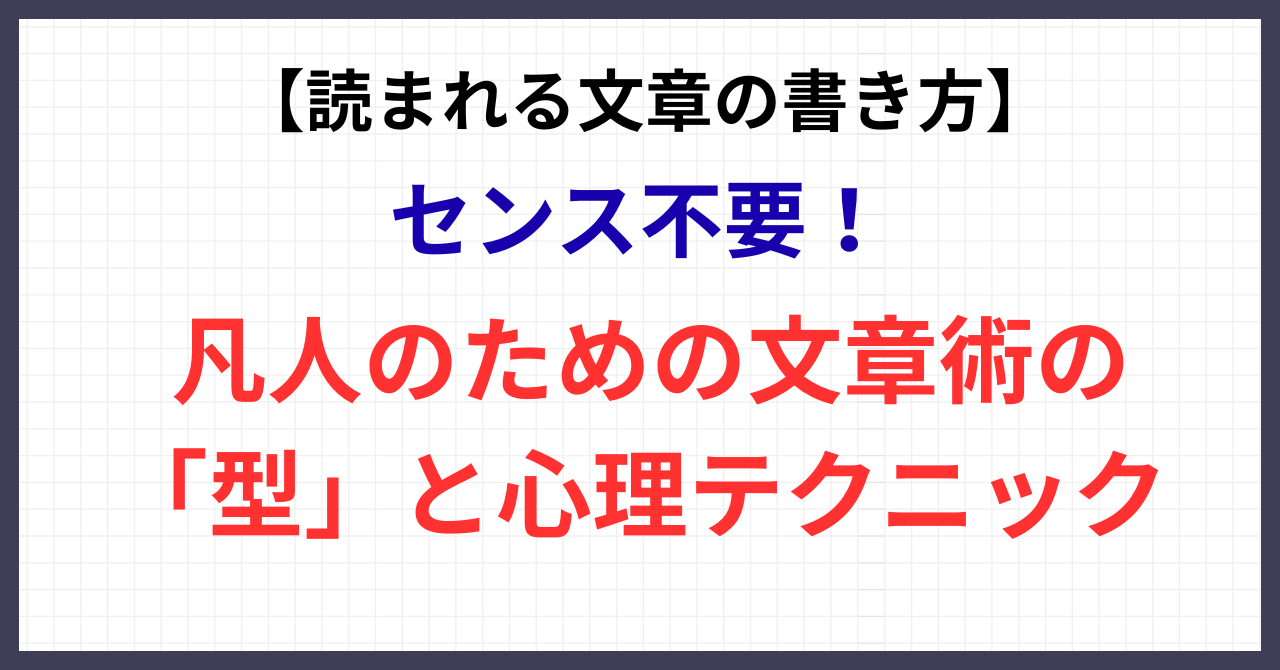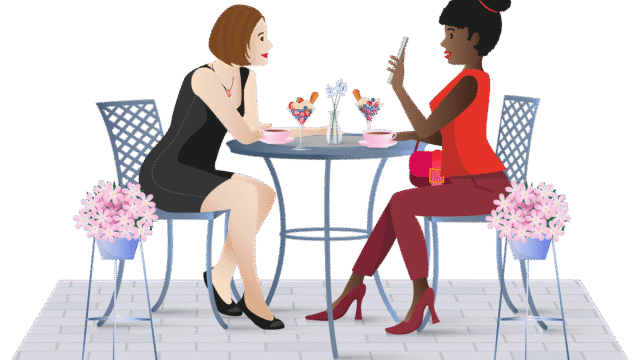「時間をかけて、想いを込めて書いたのに、誰にも読まれていない…」
パソコンの画面に表示される、ほとんど動かないアクセス数を見て、あなたは今、そんな風に肩を落としているかもしれません。
「伝えたいことはたくさんあるのに、うまく言葉にできない…」
まるで、自分のすべてを否定されたような孤独感と、どうしようもない無力感。
その気持ち、痛いほどわかります。
ボク自身も、自分の書いた文章が誰にも届かず、ブログのアクセス数が1日2桁だった時代が長く続きました。
何度も書くことをやめようと思った経験があるからです。
もし、あなたが今、文章を書くことに自信をなくし、辛いと感じているのなら、どうかこの記事を閉じる前にもう少しだけ時間をください。
断言します!あなたの文章が読まれないのは、決してあなたのせいではありません。
文章が読まれない原因は、「才能」や「生まれ持ったセンス」の問題ではないのです。
それは例えるなら、最高の食材を持っているのに、美味しい料理の作り方(レシピ)を知らないだけのようなもの。
この記事は、あなたのその素晴らしい食材(伝えたい想い)を、誰もが「美味しい!」と感動する最高の一皿に仕上げるための、具体的な「レシピ」です。
実際にボクがこの「レシピ」を実践し、クライアントの記事を添削したところ、検索順位が50位圏外から3位に上昇した実績もあります。

この記事を最後まで読み終える頃には、あなたは以下のものを手にしているはずです。
1.なぜ自分の文章が読まれないのか、その根本原因がわかる「5つの診断チェック」
2.明日からすぐに使える、人の心を動かす文章の「具体的な型(かた)」と「技術」
3.もう二度と「何を書けばいいか分からない」と迷わなくなる、書く前の「シンプルな準備方法」
文章力は、一部の特別な人のための才能ではありません。
正しい「型」と「技術」を知り、練習すれば、誰でも必ず上達するスキルです。
事実、「この方法を試したら、ブログに初めて温かいコメントがもらえました!」といった嬉しいご報告もいただいています。
さあ、もう一人で悩むのは終わりにしましょう。
あなたのその素晴らしい想いを、本当に届けたい人へ届けるための旅を、ここから一緒に始めませんか?
名前:kane
活動:無料ブログ専門のWEBライター。
「伝わる表現の伴走者」として、Amebaブログ・noteやメルマガで個人の”表現したい”気持ちをサポート。
これまで様々なジャンルのブログ記事を、200件以上の記事を添削・アドバイス。
想い: 元々は”他人に言葉を伝える”という行為が苦手”で、自分の「好き」が伝わらない失敗も多々経験。
その経験から、「センス」ではなく「技術」で表現力を高める方法を発信中。
・Ameba:https://ameblo.jp/kanegtr/
第1章:【診断】あなたの文章が“伝わらない”5つの病

「私の文章、どこがダメなんだろう…」
そう思っていても、自分一人で間違いを見つけるのはとても難しいものです。
そこで、まず最初に、多くの人が知らず知らずのうちに陥ってしまっている「伝わらない文章」の共通点を、5つの「病」としてご紹介します。
あなたご自身の文章と照らし合わせながら、「あ、これ、私のことかも…」と思うものがないか、チェックしてみてください。
原因がわかれば、解決策はすぐそこです。
【病状1:自己満足な書き出し病】
これは、書きたいことから書き始めてしまい、読者が一番知りたい「結論」がいつまで経っても出てこない文章のことです。
1.記事の冒頭が、天気の話や最近の個人的な出来事から始まっている。
2.「この記事では〇〇について解説します」という案内がなく、読み進めないと何の話かわからない。
3.一番伝えたい大切なことが、いつも文章の最後に書かれている。
読者はとても忙しく、常に「この記事は、自分にとって読む価値があるのか?」を判断しています。
最初の数行で「知りたいことが書いてありそう!」と思えなければ、残念ながらすぐにページを閉じてしまうのです。
【病状2:専門用語でドヤ顔病】
これは、自分が詳しい分野について書くときに、つい難しい言葉や業界用語をそのまま使ってしまう症状です。
書き手は親切に説明しているつもりでも、読者は宇宙語を聞かされているように感じてしまいます。
1.ブログで「SEO」「コンバージョン」「ペルソナ」などの言葉を、説明なしで使っている。
2.上司への報告書で、当たり前のように専門用語や略語を並べている。
3.読み手がどれくらいの知識を持っているか、考えずに書いている。
どんなに素晴らしい内容でも、言葉の意味が通じなければ、その価値はゼロになってしまいます。
「こんなことも知らないの?」という態度は、読者を置き去りにし、心を閉ざさせてしまう一番の原因です。
【病状3:一文が長すぎる病】
というように、読点(、)で文章を際限なく繋げてしまい、一文がとても長くなってしまう病気です。
1.気づくと、一文に読点(、)が5個も6個も入っている。
2.主語(「誰が」「何が」)と述語(「~した」「~です」)が遠く離れていて、文章のねじれが起きている。
3.声に出して読んでみると、途中で息が苦しくなる。
長い文章は、読んでいるだけで読者を疲れさせてしまいます。
どこで意味が区切れるのか分かりにくく、内容を理解するのに余計なエネルギーを使わせてしまうのです。
【病状4:同じ語尾の繰り返し病】
文章の終わりが、すべて同じ調子で続いてしまう症状です。
「〇〇でした。△△でした。そして、□□でした。」
このように、同じ語尾が3回以上続くと、文章は途端に単調になり、読んでいる人を眠たくさせてしまいます。
まるで、抑揚のない校長先生の話を聞いているようなものです。
【病状5:「誰でも書ける」コピペ風病】
これは、インターネットで調べた情報をまとめただけで、書き手である「あなた」の存在が全く感じられない文章のことです。
どこかのサイトに書いてあったような、当たり障りのない情報だけで構成されています。
1.文章の中に、あなた自身の体験談や失敗談が一つも出てこない。
2.「こう感じた」「こう思った」という、あなたの感情が全く書かれていない。
3.この記事を、なぜ「あなた」が書いているのか、その理由がわからない。
情報は、今の時代どこにでも溢れています。
そんな中で読者が本当に求めているのは、情報そのものよりも、
「あなただからこそ語れる言葉」
なのです。あなたの体験や感情が乗っていない文章は、読者の心を動かすことはできません。
さあ、いかがでしたか?
もし、一つでも当てはまるものがあったとしても、全く落ち込む必要はありません。
病名がわかったということは、正しい治し方がわかるということです。
そして、これらの病を治すための特効薬は、実は小手先のテクニックではありません。
次の章では、多くの人が見落としている、最も大切な「大前提」についてお話しします。
① 自己満足な書き出し病: 結論が最後までわからず、読者が冒頭で離脱してしまう。
② 専門用語でドヤ顔病: 難しい言葉で読者を置き去りにしてしまう。
③ 一文が長すぎる病: 文章が読みにくく、読者を疲れさせてしまう。
④ 同じ語尾の繰り返し病: 文章が単調になり、眠気を誘ってしまう。
⑤ 「誰でも書ける」コピペ風病: あなた自身の体験や感情がなく、誰の心にも響かない。
第2章:大前提:読まれる文章は「書く前」に9割決まる

多くの人は、「文章術」と聞くと、美しい言葉の選び方や、巧みな表現方法といった「書き方」のテクニックを想像します。
しかし、本当に大切なのはそこではありません。
読まれる文章が書けるかどうかは、パソコンに向かって文字を打ち始める「前」の準備段階で、すでに9割が決まっています。
家を建てる時に、いきなり木を切り始めたり、釘を打ち始めたりする人はいませんよね。
必ず最初に、どんな家を建てたいのか、誰が住むのかを考え、詳細な「設計図」を作ります。
文章も、これと全く同じです。
設計図なしに書き始めるのは、コンパスも地図も持たずに航海に出るようなもの。
どんなに頑張って進んでも、目的地にはたどり着けません。
では、文章における「設計図」とは何でしょうか? それは、たった3つのことを決めるだけです。
|
これだけです。一つずつ、見ていきましょう。
1. 【誰に?】たった一人の「あなた」を決める(ペルソナ設定)
「たくさんの人に読んでほしい」
そう思う気持ちは、とてもよく分かります。
しかし、これが一番の落とし穴なのです。
「みんな」に向けて書いた文章は、結局、誰の心にも深くは響きません。
当たり障りのない、ぼやけた内容になってしまうからです。
そうではなく、
たった一人の、特定の人物
を思い浮かべてください。
その人に向けて、手紙を書くように文章を綴るのです。
例えば、この記事のターゲット読者である「伊藤 恵さん」を例に考えてみましょう。
【この記事が届けたい、たった一人の読者(ペルソナ)】
名前: 伊藤 恵(いとう めぐみ)さん
年齢: 32歳
家族: 夫と4歳の娘の3人暮らし
状況: 半年前にブログを始めた主婦。子育ての合間を縫って、自分の経験や想いを記事にしているが、ほとんど読まれず心が折れかけている。
悩み: 「私なんかが書いても意味ないのかな…」と自信をなくし、社会から取り残されたような孤独感を感じている。
本当の願い: 上手な文章を書きたいわけじゃない。ただ、自分の言葉に「わかるよ」と共感してくれる人が一人でもいてくれたら、それだけで嬉しい。文章を通じて誰かと繋がり、もう一度、自分に自信を持ちたい。
どうでしょうか?
ここまで具体的に一人の人物を想像すると、「恵さんを励ましたい」「恵さんの役に立ちたい」という気持ちが湧いてきませんか?
「皆さん、文章で悩んでいませんか?」と呼びかけるよりも、
「恵さん、文章が読まれなくて、辛いですよね…」
と語りかける方が、ずっと心に響く言葉が生まれる気がしませんか?
これが、「たった一人のあなた」に書くことの力です。
【ボクの失敗談①】八方美人な記事を量産していました…
私も昔は、「とにかくたくさんの人に読まれたい!」という気持ちが強く、誰にでも当てはまるような記事ばかりを書いていました。
例えば、
「初心者から上級者まで、すべての人におすすめの〇〇!」
といった具合です。
しかし、そんな記事は誰からも「私のための記事だ!」とは思ってもらえませんでした。
アクセスは全く伸びず、コメントもつかない。
まるで、広い海に向かって一人で叫んでいるような気分でした。
「たった一人でいい。その人の心を鷲掴みにするんだ」
そう覚悟を決めて、特定の悩みを抱えた一人に向けて書くようになってから、初めて「この記事に救われました」という反応をもらえるようになったのです。
2. 【何を?】一番深い「悩み」に寄り添う
届けたい「たった一人」が決まったら、次はその人が
「夜も眠れないほど、本気で悩んでいることは何か?」
を考えます。
恵さんの場合、表面的な悩みは「文章がうまく書けないこと」です。
しかし、その奥にあるもっと深い悩みは、
「社会との繋がりを感じられず、自信を失っている」
という心の痛みです。
読まれる文章は、この一番深い悩みに寄り添い、「大丈夫、その悩み、解決できますよ」と優しく手を差し伸べます。
3. 【どうなる?】最高の未来(ゴール)を示す
最後に、この記事を読み終えた後、
「その人にどうなってほしいのか?」
を決めます。
これを「ゴール」と呼びます。
そして、この記事のゴールは、恵さんが「文章術の専門家になること」ではありません。
「なんだ、私にも書けるかも!もう一度、頑張ってみよう!」
と、書くことへの自信と希望を取り戻し、晴れやかな気持ちでパソコンに向かうこと。
このゴールが明確だからこそ、文章の軸がブレません。
どの章で何を伝えるべきか、どんな言葉を選ぶべきかが、自然と決まってくるのです。
「書く前が9割」の意味、お分かりいただけたでしょうか?
さあ、いよいよ設計図は完成です。
次の章から、この設計図を元に、読者の心を掴んで離さない具体的な「書き方の技術」を学んでいきましょう。
文章は書き始める前の「設計図」作りが最も重要です。
1.【誰に?】を決める: 「みんな」ではなく「たった一人の読者(ペルソナ)」に向けて書くことで、文章が深く響くようになる。
2.【何を?】を考える: その読者が抱える「一番深い悩み」に寄り添い、解決策を提示する。
3.【どうなる?】を明確にする: 読んだ後にどうなってほしいかという「ゴール」を決めることで、文章の軸がブレなくなる。
第3章:読者の心を掴んで離さない読まれる文章の書き方【実践編】

ここからは、あなたの「伝えたい想い」を読者の心にまっすぐ届けるための、具体的な文章テクニックをご紹介します。
どれも難しいものではなく、意識するだけで今日からすぐに使えるものばかりです。
たくさんの【悪い例】と【良い例】を用意したので、その違いを体感しながら読み進めてみてください。
冒頭文の黄金法則:最初の1秒で心をつかむ
読者は、記事を開いて最初の数行で「続きを読むか、読まないか」を決めます。
この勝負の数秒を制するための、3つの黄金法則があります。
(※人を惹きつけるタイトルの付け方について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
法則①:結論ファースト
読者が一番知りたい「結論」や「答え」を、最初に伝えましょう。
【悪い例】
先日、友人とカフェに行ったのですが、そこで食べたケーキがとても美味しくて…。そういえば、文章を書く時って、書き出しに悩みませんか?
色々な書き方がありますが、大切なポイントをこれからご紹介します。
【良い例】
実は、多くの人が知らない“ある3つの法則”を冒頭で使っていない、ただそれだけなのです。
この記事では、誰でもすぐ真似できる「読者の心を掴む書き出しの法則」を具体的に解説します。
【ポイント】
悪い例は、本題に入るまでが長く、読者は「で、結局何の話?」とイライラしてしまいます。
良い例は、最初に「原因は〇〇です」「この記事では〇〇を解説します」と明確に伝えているため、読者は安心して読み進めることができます。
法則②:共感
読者の悩みや痛みに寄り添い、「あなたのための記事ですよ」というメッセージを伝えます。
【悪い例】
文章力を向上させるためのテクニックを学びましょう。
【良い例】
もし、あなたが今、そんな風に一人で肩を落としているのなら、この記事はあなたのためのものです。
その悩み、痛いほどわかります。
【ポイント】
悪い例は、正論ですがどこか他人事です。
良い例は、読者が抱える具体的な悩みのシーンを描写し、「わかるよ」と語りかけることで、一気に読者との心の距離を縮めています。
法則③:未来の提示(ベネフィット)
この記事を読むことで、読者がどんな素晴らしい未来を手にできるのかを具体的に示します。
【悪い例】
【良い例】
【ポイント】
「コツを紹介します」という事実(メリット)だけでなく、「スラスラ書けるようになる」という、読者にとっての嬉しい未来(ベネフィット)を伝えることで、「読んでみたい!」という気持ちを強く刺激します。
本文でスラスラ読ませる7つの技術
冒頭で心を掴んだら、次は読者を飽きさせずに最後まで導くための技術です。
技術①:PREP法 ~最強の「型」を使おう~
PREP(プレップ)法とは、
「結論(Point) → 理由(Reason) → 具体例(Example) → 結論(Point)」
の順番で話を進める、魔法のように分かりやすい文章の型です。
どんな文章にも使える最強のフレームワークなので、これだけは絶対に覚えてください。
【PREP法の構成】
P(結論): 私は、〇〇だと思います。(まず結論を言う)
R(理由): なぜなら、〇〇だからです。(理由を説明する)
E(具体例): 例えば、こんなことがありました。(具体例でイメージしやすくする)
P(結論):だから、私は〇〇だと思うのです。(最後にもう一度、結論で締める)
【悪い例】(若手社員Bくんが、PREP法を知らずに上司に報告)
それで、いくつか確認したい点も出てきまして、B社の事例なども参考にした方が良いかと思い、今、資料を集めているところです。
ですので、ご報告が遅れております。
【良い例】(PREP法を使って報告)
(R理由) なぜなら、先方から追加要望のあった新機能について、より精度の高い見積もりと、実現可能かどうかの技術的な検証に、もう少し時間が必要だと判断したためです。
(E具体例) 具体的には、過去のB社の類似案件と比較検討し、潜在的なリスクを洗い出したいと考えています。
(P結論) 以上の理由から、より良いご提案をさせていただくためにも、2日間の猶予をいただきたく存じます。
【ポイント】
悪い例は、言い訳から始まり、何が言いたいのか(結論)が最後まで分かりません。
良い例は、最初に「何をしたいのか」が明確なので、聞く側はストレスなく内容を理解できます。
【ボクの失敗談②】「で、結論は?」と一蹴された若手時代…
ボクが社会人になりたての頃、まさにこの悪い例のような報告ばかりしていました。
頭に浮かんだ順番で一生懸命話すのですが、いつも上司には
「…で、結論は何?」
「何が言いたいのか分からない」
と、イライラさせてばかり。
このPREP法を知ってからは、報告だけでなく、メールや企画書など、あらゆる仕事のコミュニケーションが劇的にスムーズになりました。
ボクにとって、まさに人生を変えてくれた「型」です。
PREP法のシーン別の詳しい活用法は、下記の記事で詳しく解説しています⇩。
技術②:一文は短く ~息継ぎをさせてあげよう~
一文の長さは、
多くても60文字くらい
を目安にしましょう。
意識的に「。」(句点)を打つ回数を増やすだけで、文章は驚くほど読みやすくなります。
【悪い例】
【良い例】
最も重要なのは、読者の悩みを解決する質の高い記事を作ることです。
しかし、それだけでは十分ではありません。
キーワード選定や内部リンクの最適化といった、SEO対策も大切です。
この両方を、バランス良く進めていく必要があります。
(1文あたり最大30文字)
【ポイント】
内容を変えずに、ただ文章を短く区切っただけです。
良い例の方が、圧倒的にスラスラと頭に入ってくるのが分かると思います。
技術③:箇条書き・会話文 ~見た目を整えよう~
文章がずっと文字だけで続くと、読者は圧迫感を感じて疲れてしまいます。
そんな時は、箇条書きや会話文を使って、見た目に変化をつけましょう。
【悪い例】(箇条書きなし)
【良い例】(箇条書きあり)
コツ1: 結論から書く
コツ2: 一文を短くする
コツ3: 具体的な数字を入れる
【会話文の例】
kane:そうなんです。
会話文も、難しい内容を少し柔らかく伝えたい時に効果的ですよ。
【ポイント】
これらは、内容を整理し、読者が視覚的に休憩できる「余白」を作る効果があります。
適度に使うことで、文章にリズムが生まれます。
技術④:接続詞を効果的に ~話の流れを案内しよう~
接続詞は、文章と文章を繋ぐ「案内役」です。
正しく使うことで、話の展開がスムーズになります。
✅だから・したがって(順接): 前の文が原因・理由になる
雨が降ってきた。だから、傘をさした。
✅しかし・でも(逆接): 前の文と反対のことを言う
急いで駅へ向かった。しかし、電車は行ってしまった後だった。
✅なぜなら(理由): 理由や原因を説明する
私は犬が好きだ。なぜなら、とても癒されるからだ。
技術⑤:漢字とひらがなの黄金比 ~優しさを演出しよう~
文章の中で、漢字が多すぎると、堅苦しく威圧的な印象を与えてしまいます。
逆に、ひらがなが多すぎると、幼稚で読みにくい印象になります。
一般的に、読みやすい文章の漢字とひらがなの比率は
「3:7」
だと言われています。
パソコンで変換するとすぐに出てくる漢字でも、あえてひらがなで書く(「ひらく」と言います)ことで、文章の印象はぐっと柔らかくなります。
【ひらくと良い漢字の例】
- 事 → こと (そんなことはない)
- 時 → とき (嬉しいとき)
- 物 → もの (食べもの)
- 〜して下さい → 〜してください
- 〜致します → 〜いたします
- 更に → さらに
- 及び → および
- 是非 → ぜひ
技術⑥:具体的な数字と固有名詞 ~説得力を高めよう~
「すごい」「たくさん」「良い」といった、あいまいな言葉は避けましょう。
代わりに、具体的な数字や、誰もが知っている名前(固有名詞)を使うことで、文章の説得力は一気に増します。
【悪い例】
有名な俳優もおすすめしている、とても良い商品です。
【良い例】
俳優の〇〇さんも愛用していると、雑誌『anan』で紹介された商品です。
【ポイント】 どちらが「信じられるか」「イメージしやすいか」は、一目瞭然ですよね。具体性は、信頼性の源です。
技術⑦:比喩表現 ~難しいことを身近にしよう~
比喩(ひゆ)とは、「たとえ話」のことです。
難しいことや、イメージしにくいことを、読者が知っている身近なものに例えてあげることで、理解をぐっと深めることができます。
【悪い例】
【良い例】
一番太い幹になるのが「まとめ記事(ピラーページ)」で、そこから伸びるたくさんの枝が
「個別記事(クラスターページ)」です。
枝と幹がしっかり繋がっていることで、Googleから「この木は〇〇というテーマの、立派な専門の木だな」と認識してもらえます。
【ポイント】
良い例のように、誰もが知っている「木」に例えることで、専門的な内容もすっと頭に入ってきます。
例え話が上手くなると、どんな難しい内容でも分かりやすく伝わり、どの知識レベルの層にも喜んで読んでもらえるようになります。
「どんな難しい内容でも、一瞬で相手に理解させる上手な例えのコツ」を、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください⇩。
① 冒頭文の黄金法則: 「結論ファースト」「共感」「未来の提示」で読者の心を掴む。
② PREP法: 「結論 → 理由 → 具体例 → 結論」の最強の型で、驚くほど分かりやすく伝える。
③ 一文は短く: 1文60文字を目安に句読点「。」を使い、読みやすさを意識する。
④ 箇条書き・会話文: 見た目に変化をつけ、文章のリズムを整える。
⑤ 接続詞を効果的に: 「しかし」「なぜなら」などを正しく使い、話の流れをスムーズにする。
⑥ 漢字とひらがなの比率: 「3:7」を目安に、柔らかい印象を与える。
⑦ 具体的な数字と比喩表現: 説得力を高め、難しいことを分かりやすく伝える
第4章:書いた文章を「作品」に昇華させる推敲と仕上げの作法

お疲れ様でした! ここまでで、文章の設計図を作り、具体的な技術を使って本文を書き上げることができました。
しかし、ここで「完成!」と公開ボタンを押してしまうのは、少しだけ待ってください。
書き上げたばかりの文章は、まだ「素材」の状態です。
ここから、不要な部分を削り、磨き上げる
「推敲(すいこう)」
という最後の工程を経て、初めて読者に届けるべき「作品」へと昇華するのです。
推敲とは、簡単に言えば「見直し」のこと。
このひと手間をかけるかどうかが、プロとアマチュアを分ける大きな違いだと言っても過言ではありません。
具体的な推敲(見直し)のテクニック
ただ何となく読み返すだけでは、間違いは見つかりません。
効果的な4つのテクニックをご紹介します。
1. 声に出して読む(音読)
これは、最も簡単で、最も効果的な方法です。
声に出して読む最大の目的は、
「文章のリズム」をチェックすること。
これは、実際に声に出して読まないと分かりません。
黙読では気づかなかった、文章の「リズム」の悪さに気づくことができます。
✅読んでいて、つっかえる場所はないか? → 一文が長すぎる、言葉の繋がりが不自然
✅息が苦しくなる場所はないか? → 読点(、)の位置がおかしい、文章を区切るべき
✅同じ語尾が続いて、単調になっていないか? → 語尾に変化をつける
騙されたと思って、ぜひ一度試してみてください。
自分の文章の欠点が、面白いほどよく分かります。
2. 時間を置いて読む
書き終えた直後は、頭が興奮していて、自分の文章を客観的に見ることができません。
最低でも1時間、できれば一晩寝かせてから読み返してみましょう。
すると、書いている時には完璧だと思っていた文章の、おかしな点や分かりにくい部分が、まるで他人の文章を読んでいるかのように見えてきます。
この「客観的な視点」を取り戻すことが、推敲では非常に重要です。
3. 読者の視点で読む
ペルソナ(この記事で言えば、伊藤恵さん)になりきって、文章を読んでみましょう。
そして、自分にこう問いかけてみてください。
✅「途中で、意味が分からない場所はなかった?」
✅「で、この記事を読み終えた私は、次に何をすればいいの?」
特に最後の質問は重要です。
読んだ後、読者が具体的な次の一歩を踏み出せるような案内がされているか、必ず確認しましょう。
4. 誤字脱字チェックツールを使う
最後は、人間の目では見逃しがちな細かい誤字脱字を、便利なツールに頼って効率化しましょう。
無料で使える高機能なものがたくさんあります。
例えば、「Enno」や「文賢(ぶんけん)」といったツールが有名です。
文章をコピー&ペーストするだけで間違いを指摘してくれるので、公開前の最終チェックとして必ず行うようにしましょう。
「完璧な文章」より「昨日の自分より良い文章」を
ここまで推敲の重要性をお話ししましたが、一つだけ忘れないでほしいことがあります。
それは、
「完璧な文章を目指さない」
ということです。
推敲を突き詰めれば、直したい箇所は無限に出てきます。
しかし、それではいつまで経っても記事を公開することができません。
大切なのは、100点満点の文章を書くことではありません。
昨日の自分が書いた文章よりも、今日の自分は少しだけ上手く書けた。
その小さな成長を喜び、まずは世に出してみることです。
文章は、公開してからだって、いつでも修正することができます。
どうか、自分を追い詰めすぎないでくださいね。
① 声に出して読む(音読): 文章のリズムの悪さや読みにくい箇所を発見する。
② 時間を置いて読む: 客観的な視点を取り戻し、冷静に文章をチェックする。
③ 読者の視点で読む: 「悩みは解決されたか?」「次に何をすればいいか?」を自問する。
④ 誤字脱字チェックツールを使う: 最後はツールで効率的にミスをなくす。
⑤ 完璧を目指さない: 100点満点ではなく「昨日より良い文章」を目指す気持ちが大切。
第5章:「読まれる文章の書き方」について、よくある質問(FAQ)

ここで、読者の方からよくいただく質問とその回答をいくつかご紹介します。
Q1. 雑記ブログでも「読まれる文章の書き方」は同じですか?
はい、基本的に同じです。
この記事で紹介した「たった一人に届ける」「PREP法を使う」などの考え方や技術は、どんなジャンルのブログでも通用します。
ただし、雑記ブログの場合は、記事のテーマが多岐にわたるため、
記事ごとに「誰に届けたいか」をより明確に意識することが大切になります。
「コスメの記事なら20代のメイク初心者の女性へ」
「ガジェットの記事なら40代の機械に詳しくない男性へ」
というように、その都度ペルソナを切り替えるイメージを持つと、それぞれの記事の質がぐっと上がりますよ。
Q2. 文章を書くのがどうしても苦手なのですが、何から始めればいいですか?
そのお気持ち、とてもよく分かります。
最初から長い文章を書こうとすると、誰でも苦しくなってしまいます。
まずは、
「書くことへのハードルを極限まで下げる」
ことから始めましょう。
この記事の最後でも提案しますが、
「今日の出来事をPREP法で3行だけ書く」
という練習が本当におすすめです。
慣れてきたら、SNSで好きなものについて短い文章で発信するのも良いでしょう。
「書くことは、楽しいことなんだ」と脳に思わせることが、苦手意識を克服する一番の近道です。
Q3. SNSで読まれる文章の書き方に特有のコツはありますか?
X(旧Twitter)やInstagramなど、SNSの文章では、ブログ記事とは少し違うコツも必要になります。
✅冒頭の1行がすべて: タイムラインで指を止めてもらうため、最初の1行に最もインパクトのある言葉や問いかけを持ってきましょう。
✅改行と絵文字を効果的に使う: スマホで読まれることを意識し、適度な改行、空白行、絵文字を使って、視覚的に読みやすくする工夫が非常に重要です。
✅「共感」を最優先する: SNSはコミュニケーションの場です。有益な情報だけでなく、「わかる!」「私も同じ!」と思ってもらえるような、感情に訴えかける投稿が読まれやすい傾向にあります。
とはいえ、PREP法のような論理的な型はSNSでも強力な武器になります。
Q4. おすすめの文章術に関する本はありますか?
世の中には素晴らしい本がたくさんありますが、もしボクが初心者の方に「まず1冊だけ」と聞かれたら、以下の2冊をおすすめします。
✅『20歳の自分に受けさせたい文章講義』(古賀 史健 著): 「書くことは、考えること」という本質を教えてくれる一冊。
小手先のテクニックではなく、文章の土台となる思考力を鍛えたい方におすすめです。
✅『新しい文章力の教室』(唐木 元 著): 「とにかく分かりやすく!」を追求した、非常に実践的な本です。
ナタリーというニュースサイトの研修を基にしており、読みやすい文章を書くための具体的なルールが満載です。
ただし、一番大切なのは本を読むことよりも、実際に手を動かして書くことです。
この記事の内容を一つでも実践する方が、何冊本を読むよりも文章力は向上しますよ。
【読まれる文章書き方まとめ】さあ、あなたの言葉で、物語を始めよう

長い旅路でしたが、最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
この記事でお伝えしてきたことを、最後にもう一度、簡潔にまとめます。
✅文章が読まれないのは、才能のせいじゃない。
「自己満足な書き出し病」や「一文が長すぎる病」など、原因は明確な「病」にある。
✅読まれる文章は「書く前」に9割決まる。
「たった一人の読者」を決め、その人の悩みを解決し、最高の未来へ導く「設計図」を作ることが何よりも大切。
✅「PREP法」や「一文を短く」など、具体的な技術はすぐに真似できる。
豊富な良い例を参考に、一つずつ自分のものにしていこう。
✅書いたら必ず「推敲(見直し)」をする。
音読や時間をおくことで、文章は「素材」から「作品」へと変わる。
もう、お分かりいただけたのではないでしょうか。
文章力は、才能ではありません。
正しい型と技術を学び、実践することで、誰でも、必ず、向上させることができる後天的な「スキル」です。
あなたはもう、パソコンの前で一人、自信をなくして固まる必要はありません。
あなたの手の中には、もう読まれる文章を書くための「レシピ」があるのですから。
さあ、この記事を閉じたら、ぜひ最初の一歩を踏出してみませんか?
難しく考える必要はありません。
まずは今日の出来事を、この記事で学んだ「PREP法」を使って、たった3行で良いので、スマホのメモ帳にでも書いてみてください。
(R理由)なぜなら、今まで書けなかった文章が、少しだけ書けるようになったからだ。
(P結論)だから、明日も書くのが少し楽しみだ。
そんな、小さな小さな一歩で構いません。
その一歩が、あなたの「書くこと」への自信を取り戻し、昨日とは違う未来へと繋がる、確かな一歩になるはずです。
忘れないでください。
あなたの言葉は、あなただけの体験と感情が乗った、世界でたった一つの宝物です。
そして、その言葉は、まだ見ぬ誰かの心を温め、勇気づける力を、間違いなく持っています。
さあ、あなたの言葉で、あなただけの物語を始めましょう。
あなたが書くことを通じて、自分の世界を広げ、輝いていくことを、心から応援しています。
関連記事
【人を惹きつけるタイトル例7選】センス不要!クリックされる「翻訳術」徹底解説
【PREP法例文10選】好きなもので「共感といいね」を集めるブログ・SNS発信のコツ
【例え話が上手くなる方法】今日から始める「例え力」練習ガイド – 伝わる文章のアトリエ~書くのがもっと好きになるブログ~
プレゼントコーナー
記事を読んでくれたあなたに、自分のライティングタイプが分かる、無料の診断をプレゼント中!
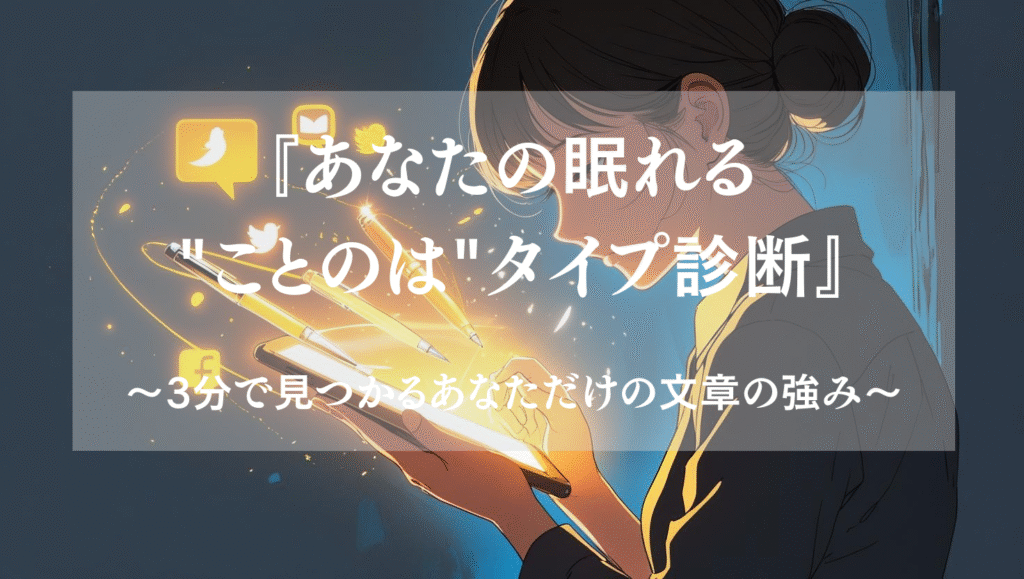
 特典: 例え力強化テンプレート(PDF)
特典: 例え力強化テンプレート(PDF)
無料診断コンテンツをご利用いただいた方限定で、下記のコンテンツの無料プレゼントをさせて頂いています⇩。