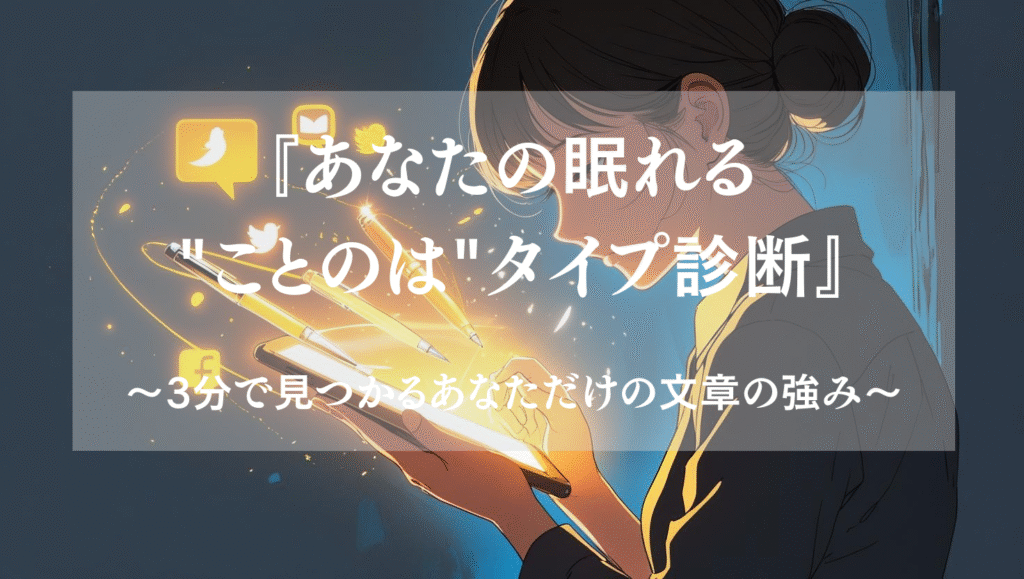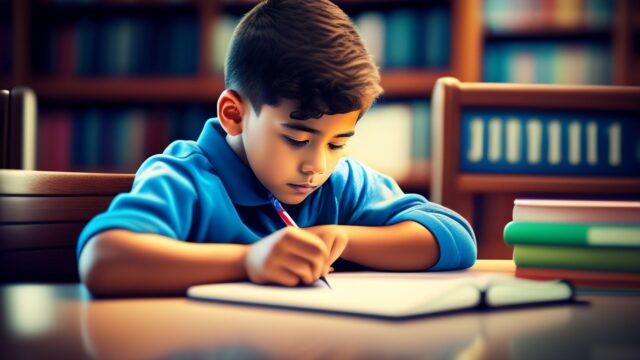「例え話が上手くなりたいけど、何から学べば良いか分からない…」
「気の利いた例えが思いつかず、具体的なフレーズやネタが欲しい…」
「良かれと思って使った例えが『うざい』と思われていないか不安…」
こんにちは!「伝わる表現の伴走者」のkaneです。
例え話が上手くなりたい、でもその「コツ」が分からない――そんな悩みを抱えていませんか?
ご安心ください。例え話の上手さは、生まれつきのセンスではありません。
正しい「コツ」を知り、少し練習するだけで、誰でも必ず上達できる「技術」です。
この記事は、これまで私が200件以上の記事添削で培ってきたノウハウと、読者の皆様のリアルな悩みのデータを元に作り上げた、「例え話」に関する全ての知識が手に入る【完全マップ】です。
この記事を上から順に読んでいくだけで、あなたは「例え話」の全体像を体系的に理解し、明日からすぐに使える具体的な武器を手に入れることができるでしょう。
いわば「例え話学習の大学の学部紹介ページ」です。
各章で「どんな知識が学べるのか」の概要を掴み、興味を持った分野の「詳細な講義(個別記事)」へと進んでください。
そもそも「例え話」とは?その絶大な効果と基本的な考え方
 本格的な学習を始める前に、なぜ私たちが「例え話」を学ぶべきなのか、その根本的な価値を確認しておきましょう。
本格的な学習を始める前に、なぜ私たちが「例え話」を学ぶべきなのか、その根本的な価値を確認しておきましょう。
多くの人が「例え話は会話のオマケ」と考えていますが、それは大きな間違いです。
例え話は、相手の心を動かすための、コミュニケーションにおける最強の武器の一つです。
なぜなら、人間の脳は「知らないこと」を「知っていること」に置き換えて理解する性質があるからです。
優れた例え話は、主に3つの絶大な効果をもたらします。
✅効果1:時短効果(難しい話を一瞬で伝わる)
複雑な概念や専門知識を、相手がすでに知っている身近なイメージに変換し、理解にかかる時間を劇的に短縮します。
✅効果2:説得力(感情に訴えかけ、納得感を生む)
単なるデータや事実だけでなく、相手の感情や原体験に訴えかけることで、話に深みと納得感をもたらします。
✅効果3:記憶力(相手の記憶に深く刻み込まれる)
ストーリーや鮮やかなイメージとして情報を伝えることで、無味乾燥な情報よりも遥かに強く、相手の記憶に残ります。
この3つの効果を理解するだけでも、例え話への意識は大きく変わるはずです。
では、ここから具体的な学習ステップに進んでいきましょう。
STEP1 そもそも「例えが上手い人」とは?【7つの共通点】

例え話の練習を始める前に、まずは私たちが目指すべきゴール、つまり「例えが上手い人」とはどんな人なのかを知っておくことが重要です。
彼らの言動や思考を分析すると、そこには以下の7つの共通した特徴が見えてきます。
- 相手の心に寄り添う“共感力”
- 豊富な「例えのネタ」のストック
- 抽象⇔具体の変換力
- イメージが浮かぶ“ビジュアライズ力”
- 「分かる!」を生む“感情・ユーモアのセンス”
- 場面ごとに調整できる“柔軟性・瞬発力”
- 「伝わらない例え」を避けるリスク管理能力
「7つの特徴、一つ一つを深く知りたい!」という方は、こちらの記事でそれぞれの特徴を深掘りし、具体的な事例を交えて徹底的に解説しています。
あなたの目指すべき姿が、より明確になるはずです。
STEP2 誰でもできる!例え話が上手くなる【5つの練習法】

「特徴は分かったけど、どうすればそうなれるの?」
というあなたのために、今日から始められる具体的な練習法を5つのステップでご紹介します。
これらは才能ではなく、意識と実践の積み重ねによって「例え筋」を鍛えるトレーニングです。
- 観察術:日常のすべてを「ネタ帳」に変える
- 思考術:「つまり?」「例えば?」を口癖にする
- 表現術:1日1個アウトプットで実践する
- 模倣術:上手い人の型を「盗んで」アレンジする
- 改善術:フィードバックをもらい、精度を上げる
「具体的なトレーニングメニューが知りたい!」
「それぞれの練習法を、毎日の習慣に落とし込むためのコツは?」
という方は、こちらの完全ガイドをどうぞ。
あなたのレベルに合わせた具体的な練習プランを提示しています。
→ 【詳細記事】例え話が上手くなる方法|5つの具体的なトレーニングメニュー
STEP3 コピペOK!すぐに使える【分かりやすい例え話フレーズ集】
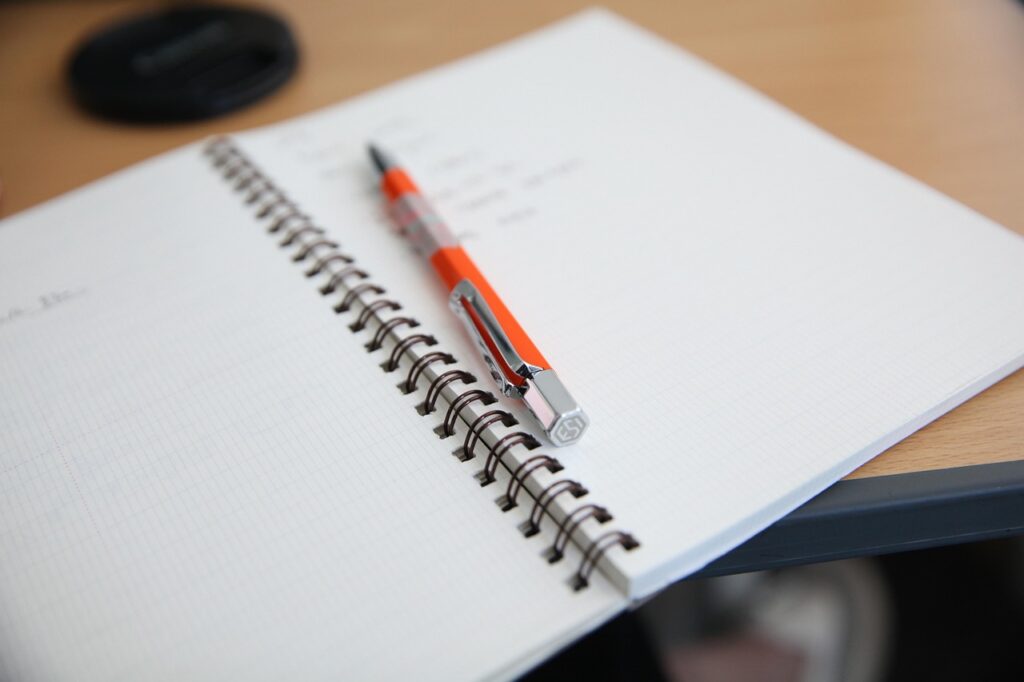 「理論はいいから、今すぐ使えるフレーズが欲しい!」という声にお応えします。
「理論はいいから、今すぐ使えるフレーズが欲しい!」という声にお応えします。
日常会話やSNSでそのまま使える、便利な例え話のフレーズをいくつかご紹介します。
まずは型を真似ることから始めてみましょう。
- (嬉しい時): 「まるで宝くじに当たったみたいに嬉しい!」
- (難しいことを説明する時): 「〇〇は、いわば△△の『土台』みたいなものです」
- (量を伝える時): 「〇〇の量は、だいたいコンビニのおにぎり2個分くらいです」
- (共感を呼ぶ時): 「〇〇するのって、初めて自転車に乗る時みたいに、ちょっと怖いですよね」
「もっとたくさんのフレーズが知りたい!」
「ビジネス、恋愛、自己紹介など、場面別の鉄板フレーズを網羅したい!」
という方は、30個の実用的なフレーズを場面別にまとめた、こちらの記事が便利です。
→ 【詳細記事】コピペOK!日常会話で使える例え話フレーズ30選
STEP4 失敗を回避する!【「うざい例え話」の重要注意点】
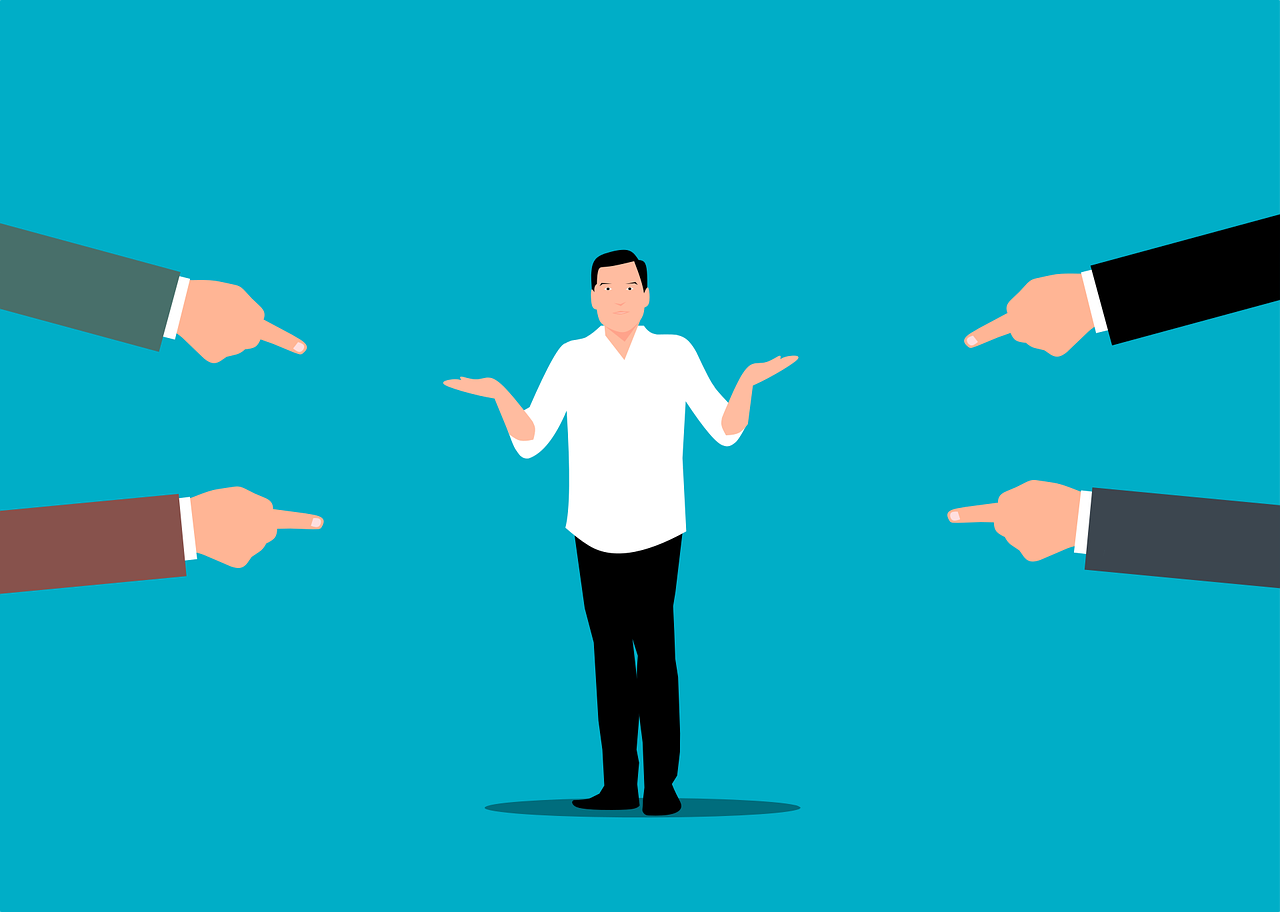 例え話を使う上で、多くの人が不安に思うのが「自分の例えが、相手を不快にさせていないか?」ということです。
例え話を使う上で、多くの人が不安に思うのが「自分の例えが、相手を不快にさせていないか?」ということです。
ここでは、絶対にやってはいけない「嫌われる例え話」の代表的なパターンを3つご紹介します。
- 相手が知らない「内輪ネタ」例え
- 見下した感じの「上から目線」例え
- 話が長いだけの「自分語り」例え
「もしスベってしまった時の、スマートなリカバリー術も知りたい!」
「他にも注意すべきNGパターンはないの?」
という方は、こちらの失敗回避マニュアルをお読みください。
転ばぬ先の杖として、あなたのコミュニケーションを守る盾となるでしょう。
→ 【詳細記事】やってはいけない!嫌われる「うざい例え」とその対策
STEP5例え話で「面白い人」と思われるコツ
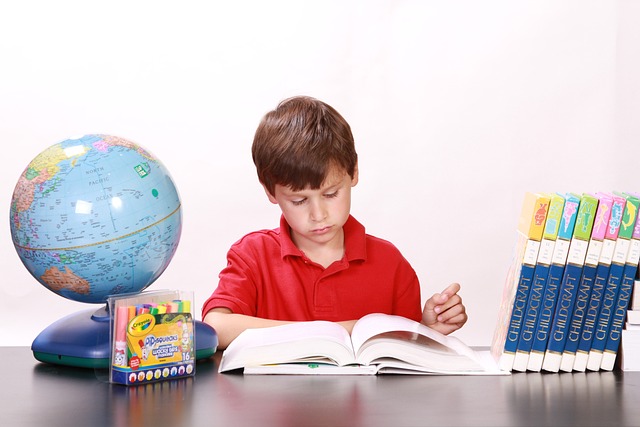
「ウチの上司、まさに鬼舞辻無惨なんですよ」
このような「分かる人にしか分からない」固有名詞を使った例えは、以外にも聞き手の心を強く引きつけ「面白い人」という印象を相手方に植え付けます。
それは、この表現が単なる「分かりやすさ」のためだけでなく、特定の相手の心に深く刺さるための「秘密の合言葉」として機能するからです。
そのメカニズムは、主に3つの理由に分解できます。
理由1:一瞬で「仲間」だと認識させ、心の壁を壊すから
固有名詞、特にアニメや漫画などのカルチャーに根差した言葉は、一種の“踏み絵”として機能します。
この瞬間に、「話し手」と「聞き手」という他人行儀な関係から、「同じ作品を愛する“仲間”」という特別な関係性へと変化します。
「このネタが分かるあなたなら、私のこの気持ち、分かってくれますよね?」
という無言のメッセージが伝わり、聞き手は無意識のうちに心を開き、より深く話を聞こうという姿勢になるのです。
「特定の深い層」にしか分からない言葉だからこそ、分かってしまった相手とは一瞬で強固な連帯感が生まれます。
理由2:言葉で説明するより「早く」「濃い」感情と文脈を届けられるから
「理不尽で、冷酷で、部下の意見を聞かず、自分の機嫌一つで全てを決定する上司。」
このように長く説明するよりも、
「鬼舞辻無惨みたいな上司。」
と言った方が、相手方に「あぁ、そりゃ大変だ…」と、圧倒的に早く、そして濃密な情報が伝わります。
これは、聞き手の脳内にある『鬼滅の刃』という巨大なデータベースに直接アクセスしているようなものです。
キャラクターの性格、物語の文脈、そしてそのシーンが持つ「恐怖」や「絶望感」といった感情のすべてを、たった一言で相手の心にダウンロードさせることができます。
これは、どんなに巧みな説明をもってしても不可能な、感情のショートカットなのです。
理由3:情景の「解像度」が飛躍的に上がり、忘れられない記憶になるから
「毎日の朝礼が厳しい」という表現は、どこか抽象的です。
しかし、「毎日の朝礼が【下弦解体のパワハラ会議】みたいなもの」と言われるとどうでしょう。
聞き手の頭の中には、具体的な情景(薄暗い部屋、恐怖に震える登場人物、絶対的支配者の理不尽な叱責)が、鮮明な“映像”として再生されます。
この「共通の映像を見る」という体験は、聞き手に強烈なインパクトを与え、ただの「話」を忘れられない「記憶」へと昇華させます。
言葉の意味を理解するだけでなく、その場の空気感や温度、湿度までをも共有するような、深いレベルでの共感が生まれるのです。
STEP6さらに高みへ!【例え力を伸ばすおすすめ本&上級テクニック】
 基本をマスターしたあなたが、さらに表現力を高めるためのヒントをご紹介します。
基本をマスターしたあなたが、さらに表現力を高めるためのヒントをご紹介します。
単に分かりやすいだけでなく、相手を深く納得させるには、物事の本質をあぶり出す「思考の型」を知ることが有効です。
✅おすすめ本: まず一冊だけ読むなら、柳田理科雄氏の『空想科学読本』がおすすめです。
複雑な科学現象を、誰もが知っている日常のイメージに変換する、まさに「例え話の教科書」です。
✅上級テクニック: 単に分かりやすいだけでなく、相手を深く納得させるには、物事の本質をあぶり出す「思考の型」を知ることが有効です。
「ひろゆき氏も使う、人を納得させる思考法とは?」――その答えはこちらの記事で解説しています。
ビジネスで応用可能な思考フレームワークが学べます。
→ 【詳細記事】ひろゆきに学ぶ「思考の型」と人を納得させる例えの技術
まとめ|このマップを手に、あなたも「伝え上手」の仲間入り
 この記事では、例え話が上手くなるための学習ステップを、網羅的な「マップ」としてご紹介してきました。
この記事では、例え話が上手くなるための学習ステップを、網羅的な「マップ」としてご紹介してきました。
例え話の上達に必要なのは、才能ではありません。
正しい知識を、正しい順番で学ぶことです。
このマップを眺めて、あなたが今どの段階にいて、次に何を学ぶべきかが見えたなら幸いです。
ぜひ、この記事をブックマークして、あなたの「例え話学習の地図」として、何度も見返しに来てください。
そして、興味を持った「STEP」から、詳細記事という冒険へと旅立ってください。
あなたの「伝えたい」という大切な気持ちが、100%相手に伝わるようになる日を、心から応援しています。
筆者プロフィール
名前:Kane
活動:Amebaブログやnoteなど「無料ブログ専門のWEBライター」として、200件以上のブログ記事を添削・アドバイス。
「伝わる表現の伴走者」として、個人の”表現したい”気持ちをサポート。
想い:元々、自分の伝えたいことを”伝えることが大の苦手”で、自分の「好き」が伝わらない失敗も多々経験。
その経験から、「センス」ではなく「技術」で表現力を高める方法を発信中。
・Ameba:https://ameblo.jp/kanegtr/
【プレゼントコーナー】
記事を読んでくれたあなたに、自分のライティングタイプが分かる、無料の診断をプレゼント中!