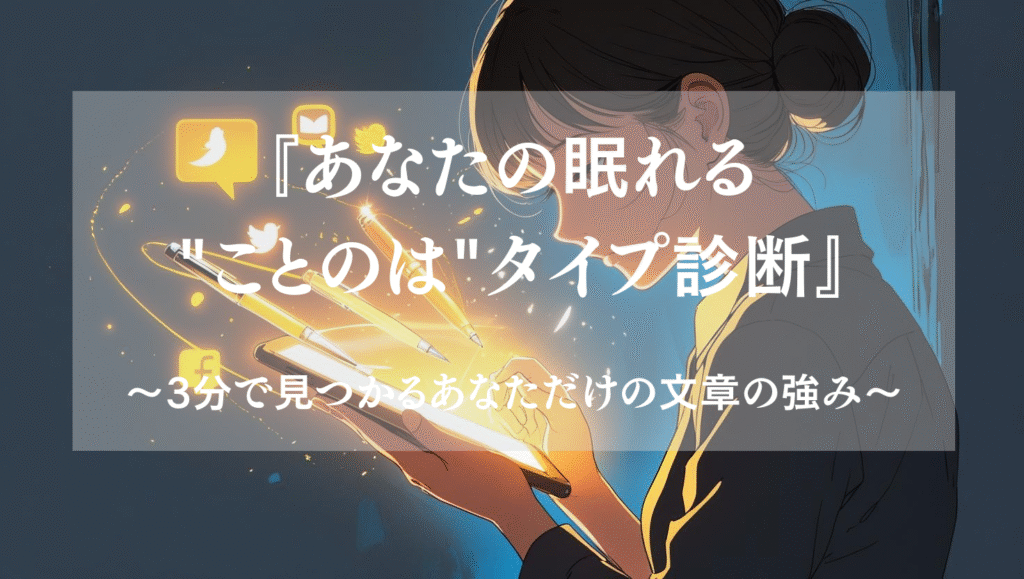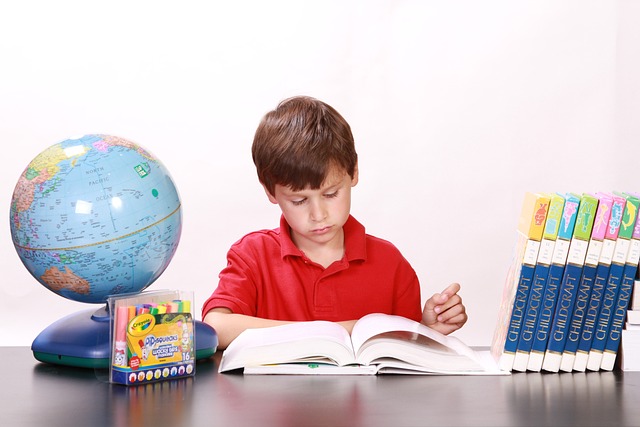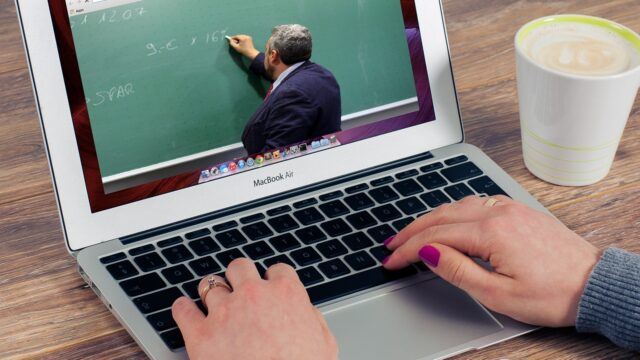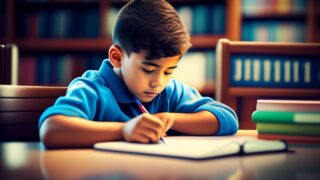「一生懸命書いたブログの感想が『よく分からない』の一言で、悲しくて…」
「SNSに投稿しても、いつもスルーされてばかり。私って文章下手なのかな…」
「noteやアメブロに記事をたくさん書いてるけど、全然反応がなくて心が折れそう」
結論から、お伝えします。
“本当に読まれる文章”を書くコツはたった一つ。
「”読ませず”に読ませられるか?」
これだけ。
「お前は、何を言っているんだ?。」
そう思うかもしれませんが、この”仕組み”を理解出来ていないと、どれだけクオリティの高い文章を書いてたとしても、一瞥すらされません。
✅ 読者に「読ませずに」読ませる文章を書くコツが掴める。
✅読者にしっかり「本質を理解してもらえる」文章が書ける。
✅「分かりやすくて読みやすいです」とコメントがもらえる。
✅ブログやSNSでの反応が3倍に増加。
✅「あなたの言葉に救われました」と感謝される。
アメブロ・noteを専門とするWEBライターであり、「伝わる表現の伴走者」です。
これまで200本以上のブログ添削を担当し、反応率2倍を達成。
ライターとしての経験を元に、ブログやSNSで使える「わかりやすい文章の書き方」と「書くことを楽しむヒント」を発信しています。
あなたの「書きたい」気持ちを、もっと自由に、もっと楽しくするのがこのブログの目標です。
・アメブロ記事はコチラ→https://ameblo.jp/kanegtr/
・note記事はコチラ→https://note.com/shiny_stilt739
読みやすい文章を書くには?“読ませずに読ませる”ための3つの条件
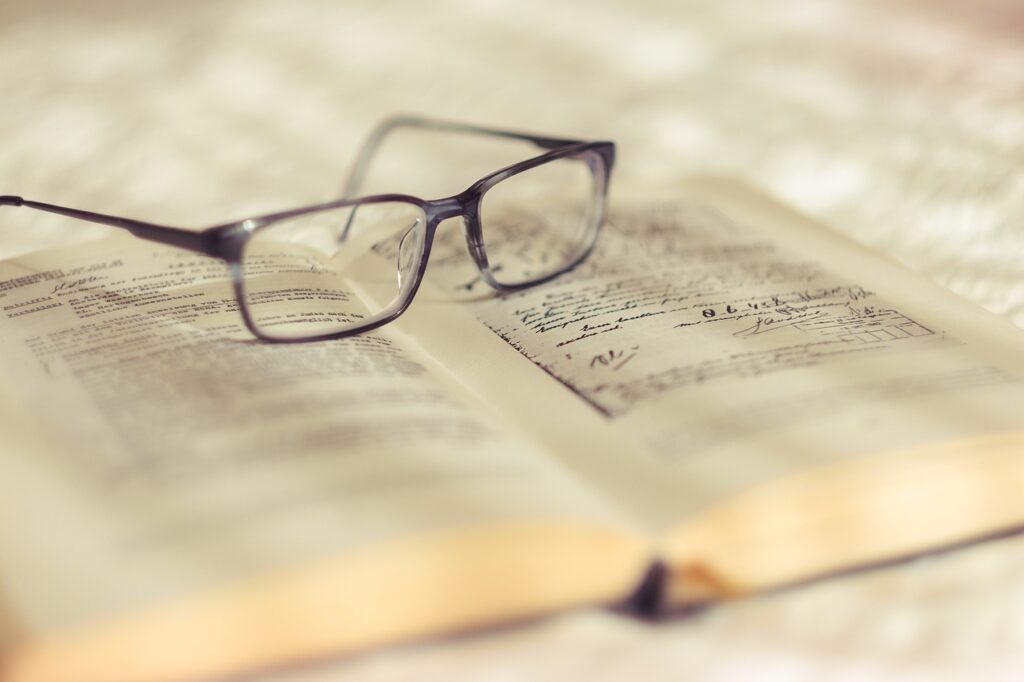
「なんか読みにくいなぁ…。」
そう感じる文章、めちゃくちゃ多くないですか?
実は、読みやすい文章には絶対的なルールがあります。
このルールを知ってるかどうかで、あなたの文章が、
「最後まで読まれるか?」
「3秒で離脱されるか?」
が決まります。
この章では、そんな「読ませずに読ませる技術」の核心部分をお伝えしていこうかと!
「これなら読みやすい文章が書けそう!」と前向きに感じていただけるはず。
一緒に楽しく、読みやすい文章を身につけていきましょう!
読みやすい文章を見抜く3つのチェックポイント
「読みやすい文章」とはズバリ「『読ませずに』読ませる技術」を駆使した文章。
その「読ませずに読ませる技術」が、以下の3つのポイント。
この3点を押さえていない文章は、ほぼ読まれません。
ええ、確実に…。
では、上記3つのポイントについて、1つづつ徹底的に解説していきます!
1:12歳の子供が読んでも理解できる文章か?
基準は、たった一つです。
「12歳の子供が読んで、即座に『あー、なるほどね!』と頷くかどうか?」
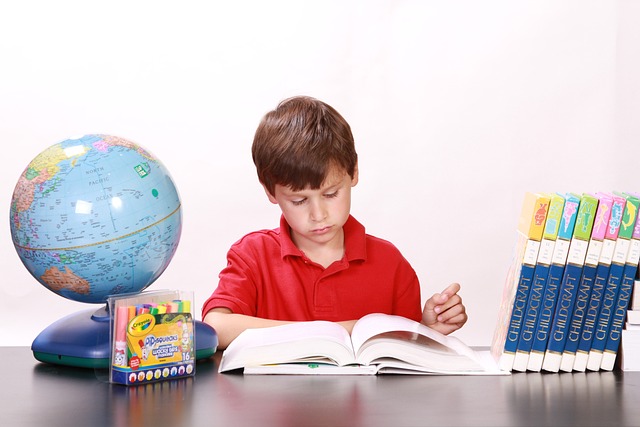
子供に理解できるものは、大人は「一読」で伝わります。
逆に言うと、子供に伝わらないものは、大人にも伝わってません。
難しい言葉を使って、複雑な構造で書いた文章。
一見「頭良さそう」に見えるかもしれませんが、読者にそんな文章は全く響きません。
しかし、「12歳の子供が読んでも『なるほど!』って思える文章」だったら、大人が読んだら即、内容を理解して行動に移せるでしょ?
そもそも、読者は「文章を読みたい」のではなく「文章から『情報』を抜き取って早く行動したい」のです。
そんな読み手に負担を掛けないためにも、この技法が必要なのです。
2. 読み飛ばしても内容を理解できる文章か?
読者は基本的に、文章を一字一句読んだりしません。
そのため「読み飛ばされても内容を理解出来る文章」でなくてはなりません。
例えば、
↑この一文で、何が伝わりますか?
何も伝わりません。
こういうのを書いちゃう人、めちゃくちゃ多いんですけど…
読者は3秒で離脱します。

なぜなら「ソリューションって何?」「ユーザビリティって何?」と、読者の脳内で翻訳作業が発生するから。
では、下記の文章ならどうでしょう?⇩。
一目瞭然ですよね。
小難しい専門用語で、長々と説明する文章は誰でも書けます。
しかし、そんな文章を一字一句丁寧に読む人はいません。
そのため、言葉の”核”をブチ抜き「流し読みしても大丈夫な文章」を書くことがポイントです。
3. 読後に何らかの行動を起こしたくなる
文章を書く最大の目的は、読後に「行動を起こしてもらうこと」です。
つまり、読み終わった後に「やってみよう」「誰かに教えたい」「保存しておこう」と思える文章であることが大事です。
そのためには『重要な情報が記憶に残る工夫』が、重要です。
いかがでしょうか?
ただ「読書をすることで知識が増えます」だと、「知識が増えたら何?どうなるの?」と、「読書して知識を増やすメリットを感じられない」ので、”知識増えること”が重要な情報であっても、記憶してくれません。
しかし、後者のように、
1:読者の悩みに言及→「今、人生に行き詰ったいる。」
2:読者の悩みの解決策→『読書による知識量の増やすこと。』
3:解決策を試すメリット→『人生の選択肢の幅が広がる。』
と、読者の「悩み」「解決策」「解決策を試すメリット」に触れることで、読者は「読書して知識を増やすことで人生の幅が広がるんだ?」と、重要な情報を記憶しやすくなります。
そして何より、
「たった10分の読書で『人生を大きく変えられるかもしれない!』」
という”簡潔”かつ”具体的でインパクトの強い”情報は、「たった10分の読書で人生を変えられるならやってみよう!」と、読み手は即行動を起こしたくなりそうですよね。
この3つの基準を満たせば、誰でも読みやすい文章が書ける
つまり、読みやすい文章とは、
「12歳でも理解でき、最後まで読めて、何かしたくなる文章」
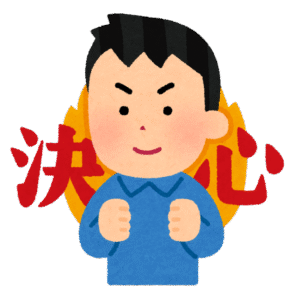
なんです。
「読みやすい文章」でブログのアクセス数が倍になった事例
実際、この3つのチェックポイントを意識することで、ブログのアクセス数を大きく改善させた事例があります。
実際、ボクが添削させて頂いた「主婦30代/note初心者」の方は、例え力を磨いた後、大きくアクセス数を伸ばしています。
実際、2025年3月1日からnoteでブログを作成し、最初の10日間は「アクセス数『1~2』」「いいね『0』」の状態でした。
しかし、上記で解説した3つのチェックポイントを意識し始めて半月辺りから、ドンッとアクセス数を伸ばしています⇩。

その後、3か月チョイで「アクセス数」「いいね」が倍以上に増え、50記事未満でありながら、安定したアクセスを獲得しています⇩。

最も注目すべき点は「コメント数の増加。」
ブログ立ち上げ時の半年間は「コメント数0」だったのが、3か月後には「コメント数8」と、劇的に増えています。
「コメントが増える」と言うことは、「読者が記事を最後まで読んでくれている」何よりの証拠!
そして多くの読者に記事の内容が共感されているということになります。
このように「読みやすい文章」は、記事アクセス数にも大きな影響を与えるのです。
読みやすい文章を書く5つの黄金法則|読者心理に刺さるテクニック集

実は、読みやすい文章には絶対的な法則があります。
しかも、それは才能とか経験じゃなくて、
「たった5つのルールを覚えるだけ。」
そこで、この章でお伝えするのは、読者の心理ニーズに基づいた下記の「5つの黄金法則」です⇩。
この5つの心理に応えることで、あなたの文章は「読みやすい!」「分かりやすい!」と必ず言われるようになります。
どれも今日から使える実践的なテクニックばかりなので、「これなら自分にもできそう!」と感じてもらえるはず。
一緒に楽しく、読者に愛される文章の書き方を身につけていきましょう!
法則1|一文50文字以内で伝わる文章に(時短ニーズ対応)
読者の時間を守る|短文で伝える効率的な書き方
「文章は短く」とよく言われますが、なぜでしょうか?。
答えは「読者の時間を大切にするため」です。

長い文章は、読者の貴重な時間を奪ってしまいます。
いかがでしょうか?
前者の長々とした説明文に比べ、後者の方が「あ、今日は『読みやすい文章の書き方を教えてくれるんだ』」と、本質を一瞬で掴めそうじゃないですか?
これは「手抜き」じゃなくて「効率化」です。
短い文章で同じことを伝えられるなら、それは高度な技術なんです。
【実践テクニック】一息ルールで自動判定
一文の長さを判断する最も簡単な方法は「一息ルール」です。
- 声に出して一息で言えない=長すぎる
- 「が」「で」「から」の接続部分で分割可能
- 電話で相手に用件を伝える感覚で
例えば電話で、
「もしもし、田中です、今度の会議の件でお聞きしたいことがあるのですが」
まで一息で言えますよね。
これが約50文字です。
これ以上長くなると、相手は「えーっと、何の話だっけ?」となってしまいます。
文章も同じです。
法則2: 安心ニーズ対応|主語と述語は10文字以内で寄り添う
主語と述語で伝わる安心感|誤解されない文章の書き方
主語と述語が離れすぎた文章は、読者を混乱させます。
これは「信頼を失う」リスクに直結します。
→ 主語「私が」と述語「作成します」が離れすぎて意味が曖昧。
→ 主語と述語が近く、誤解の余地なし。
これは恋人同士と同じです。
離ればなれになると関係が不安定になりますが、そばにいれば安心ですよね。
【実践テクニック】10文字以内ルール
主語と述語の理想的な距離は「10文字以内」です。
☑️ 主語と述語の間は10文字以内が理想。
☑️ 修飾語は後から追加する構造に。
☑️ 「誰が・何を・どうする」を最初に明確化。
この3つを意識するだけで、読者の脳に負担をかけずに済むんですよ。
なぜかというと…、
「本質が一瞬で理解できるから。」
そこで、下記の2つの例文を見比べてください。
どうですか?
後者の方が、「あ、私たちに感謝してるんだな?」と、スッと本質が頭に入ってきませんか?
「誰が・何を・どうする」を最初に伝える。 修飾語は後回し。
たったこれだけで、文章の読みやすさが劇的に変わります。
法則3|漢字3:ひらがな7のバランスで“親しみやすい文章”に
難しく見せず、分かりやすく見せる技術
文章を親しみやすくする超重要な法則をお伝えします。
それが「漢字3:ひらがな7」のバランス。
これは難しく見せず、分かりやすく見せる技術ですね。
実は、漢字が多い文章って「知的」に見えるかもしれませんが、読者を遠ざけちゃうんですよ。
例えば、こんな感じ。
どうですか?
後者の方が、圧倒的に読みやすくないですか?
これは洋服と同じです。
フォーマルすぎると近寄りがたいですが、カジュアルすぎても信頼感に欠けます。
「ちょうどいい親しみやすさ」
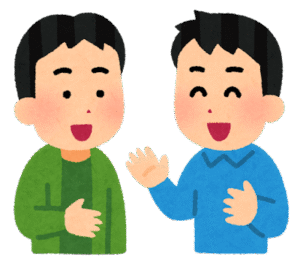
が大切なんです。
【実践テクニック】ひらく漢字の判断基準
「ひらく」とは、漢字をひらがなに変換することです。
これって、服装を「カジュアルにする」のと同じなんですよ。
例えば「 スーツ(漢字)→私服(ひらがな)」に着替えるイメージです。
フォーマルすぎると近寄りがたいけど、親しみやすい格好だと話しかけやすいでしょ?。
基本的なルール:
1:小学校で習わない漢字は基本的にひらく → 小学生が読めない漢字は「難しすぎる服装」ってこと。
2:「時」→「とき」「事」→「こと」「更に」→「さらに」 → よく使う漢字でも、ひらがなの方が優しい印象になる。
3:迷ったら「優しい印象」を選ぶ → 「どっちにしよう?」って迷ったら、親しみやすい方を選べばOK。
よくひらく漢字の例:
- 殆ど → ほとんど
- 沢山 → たくさん
- 実は → じつは
- 且つ → かつ
- 但し → ただし
【判断のコツ】
「この漢字、中学1年生の弟(妹)に読んでもらえるかな?」って考えてみてください。
「うーん、読めないかも…」って思ったら、ひらがなにしちゃいましょう。
つまり、「ひらく」は文章を親しみやすい服装に着替えさせることなんです。
難しい漢字ばかりだと「なんか偉そう…」って思われちゃうけど、適度にひらがなを混ぜると「この人、話しやすそう」って思ってもらえますよ。
法則4: 語尾バリエーション|「です・ます」連発で単調にならない技術
語尾バリエーションで魅せる|『文章上手』と思わせる技術
読者があなたの文章を3行で閉じる理由、教えましょうか。
内容がつまらない以前の問題なんです。
語尾が「です、です、です」「ます、ます、ます」このパターンだからです。
これ、お経みたいになっちゃってるんですよ。
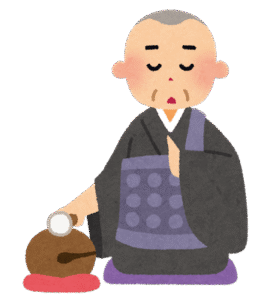
読者は神様や仏様じゃありません。
そんな単調なリズムで、心は動かないんです。
「この人、文章慣れしてるな」じゃなくて、「この人の文章、なんか引き込まれる…!」って思わせたいですよね。
でも、対策はめちゃくちゃ簡単です。
あなたの頭にこのルールを刻み込んでください。
【実践テクニック】3回ルールで自動回避
逃げ道はいくらでもあります。使える”武器”をお渡ししますね。
- 「〜でしょう」:読み手を引き込む、優しい”問いかけ”
- 「〜かもしれません」:断定を避け、含みを持たせる”揺さぶり”
- 「〜ですね」:共感を誘う、親しみやすい”確認”
- 体言止め:余韻を残し、相手に想像させる最強の”飛び道具”
これらの武器を使い分けて、文章に”緩急”と”リズム”を作るんです。
その辺にある、つまらない文章を見てみましょう。
「ブログは継続が大切です。毎日更新するのは大変です。でも続ければ成果が出ます。」
「ブログは継続が大切でしょう。だが、毎日更新するのは地獄かもしれません。それでも続けた先にこそ、本物の景色が待っている。」
どうです?リズムが、温度感が、まるで違うでしょう。
語尾のバリエーションは、文章に「音楽」を生み出すんです。
これは楽器の演奏と同じ。同じ音ばかりだと単調ですが、高低をつけると美しいメロディーになりますよね。
語尾を制する者が、文章を制します。覚えておいてくださいね。
法則5: 箇条書きは読者への思いやり|一目で分かる情報整理術
【効率性+安心感ニーズ対応】視覚的に優しい文章デザイン
あなたの文章が読まれない理由、分かりますか?。
情報がでかい”肉塊”のまま、読者の頭に突っ込まれてるからなんです。
これは”情報”じゃなくて”暴力”ですよ。

読者の脳は、そんなものを理解する前にシャットダウンしちゃいます。
これは弁当の盛り付けと同じ。
同じおかずでも、キレイに整理されてると美味しそうに見えますよね。
大事なのは、情報を”分解”し、箇条書きという名の”整理術”で、一つずつ、確実に頭に入るようにしてあげることです。
【実践テクニック】箇条書きを使うべき場面
あなたが”箇条書きを使う”べき場面は決まってます。
以下の状況になったら、迷わず箇条書きを使ってください。
✅3つ以上の情報を並べる時
✅手順や工程を説明する時
✅メリット・デメリットを示す時
✅チェックポイントを確認する時
【実践例】
その違いを、実際に見てみましょう。
「会議の議題は予算の検討と人員配置の見直しとスケジュールの調整の3点です。」
↑この一文で、読者の頭は「え?何だっけ?」ってなります
会議の議題は、以下の3点です。
1.予算の検討
2.人員配置の見直し
3.スケジュールの調整
↑情報は、一つずつ分けるから確実に理解できる。
情報を整理して見せるのは、読者への”思いやり”なんです。
これは電車の案内表示と同じ。
「次は新宿、新宿」って一つずつアナウンスするから分かりやすいんですよ。
「次は新宿と渋谷と池袋と品川です」って言われたら「え?どこで降りるんだっけ?」ってなりますよね。
情報を整理するのは、確実に伝えるための”戦略”です。覚えておいてくださいね。
まとめ|“読みやすい文章”を書く誰でも実践できるコツを再確認

読みやすい文章の本質を再確認
読みやすい文章とは、難しいテクニックのことではありません。
読者の時間を大切にし、理解の負担をできる限り軽くしてあげる「思いやり」の表現です。
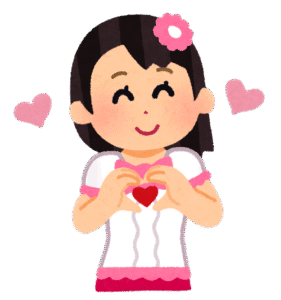
あなたが今日から実践すべき3つの核心
この記事で学んだ5つの法則の中から、まずは以下の3つを意識するだけで、あなたの文章は劇的に変わります。
あなたの文章が生まれ変わる瞬間
これらの技術は、一度身につければ一生の財産になります。
文章力は才能ではなく、知っているか知らないかの差でしかありません。
あなたも必ず変われます。
関連記事
【わかりやすい文章を書く人になるコツ】文章がスッと頭に入る「12歳理論」とは?
【プレゼントコーナー】
文章を書くのが苦手な人向けに、1分であなたのライティングタイプが分かる、無料診断はコチラ⇩。
🎁 特典: 読みやすさ診断チェックシート(PDF)
無料診断コンテンツをご利用いただいた方限定で、下記のコンテンツの無料プレゼントをさせて頂いています⇩
- 12歳テスト用質問項目
- 文章種別対応版(ブログ・メール・SNS・プレゼン)
- Before/After記録用テンプレート
- 改善ポイント発見ガイド
✨ 肩の力を抜いて、まずは自分の文章の特性を確認してみてください!。